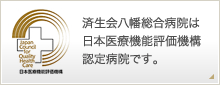- 済生会八幡総合病院 HOME
- > 診療体制
- > 診療科一覧
- > 専門医療体制
- > 腎センター
腎センター
当院腎センターは、1968年6月に米国ミルトンロイ社製の人工透析装置で西日本で最初の血液透析を開始、また1972年5月には西日本地区の一般病院としては最初に生体腎臓移植を成功した歴史ある腎疾患治療センターです。1980年1月からは、新しい透析方法としてCAPD(連続携行式腹膜透析)を導入し、1982年10月には最初の献腎移植を施行しました。また、2011年3月より在宅血液透析も行っています。
当腎センターの特長は、慢性腎不全治療としてこれらの3種類の治療方法を選択できるという点です。また、それぞれの治療について長年の経験を持つスタッフがおり、患者さんの年齢、病態や生活パターンに合わせて最適の治療方法を選べる体制になっています。腎臓移植に当たっては、手術から術後の免疫抑制方法と合併症対策まで腎センターの外科と内科のスタッフが協力して診療に当たっています。
慢性腎臓病(CKD)について
腎臓病は静かに進行することの多い病気であり、その早期においてはほとんど症状がないのが特徴です。最近、マスコミでも扱われる機会の多くなった慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)とは、検診や人間ドックでの検尿異常(尿蛋白や尿潜血)、血清クレアチニンの上昇などが3ヶ月以上続く状態です。特に血清クレアチニンの値によって腎機能(糸球体濾過値、正常では90mL/分以上)を推定し、その値が60以下(CKDステージ3以上)の場合がCKD患者とされています。
CKDへの対策
CKDは病期によってステージ1~5に分けられ、早期(ステージ1~2)には症状はほとんどありませんが、症状が出現する時期(ステージ4~5)になると腎機能を回復することが難しいという問題があります。CKDを早期に発見してステージを進行させないことが重要で、腎機能が既に低下した場合には、食事療法や薬物療法によって残された腎機能を長持ちさせることが大切です。
CKD対策の意義
現在、日本では約29万人の方が透析を受けており、毎年約1万人ずつ患者さんが増加。その原疾患としては1998年以降、糖尿病性腎症が最も多くなっています。また、CKDを持つ人は心筋梗塞、心不全および脳卒中といった心血管疾患の合併症が多くなるということが解ってきています。CKD対策を行うことは、すなわち透析となる患者さんを減らし、命を脅かす病気も減らすということになるわけです。検診で腎臓の異常を指摘された場合には、早期に腎臓専門医の受診をおすすめします。
当院ではかかりつけ医の先生方との病診連携でCKDの患者さんの定期的外来フォローを行うとともに、CKDへの教育・講演活動、また木曜日の午後の時間帯にはCKD4以上の患者さんに対して医師・看護師・薬剤師および栄養士による腎臓病教室(まめまめ教室)を開催しています。
リビング北九州「健康を考えるシリーズ」 《掲載記事》
執筆: 腎臓(移植)外科主任部長 安永 親生
専門: 腎臓移植・腎不全外科・二次性副甲状腺機能亢進症
慢性腎不全について、リビング北九州にて連載の「健康を考えるシリーズ」に掲載されました記事を紹介します。
腎センターの特徴ある診療内容とその治療成績
次に、当センターの特徴ある診療内容と活動についてその歴史、現状と将来的展望についてくわしく述べたいと思います。
1.腎臓移植と慢性腎不全治療法の選択
1970年1月、先代の合屋忠信名誉院長を中心としてHLA検査室の設置、ウマ抗ヒトリンパ球血清の作製などを行いながら、腎臓移植の準備を開始しました。その2年後の1972年5月、第1例目の生体腎臓移植が施行され、これは一般病院としては西日本地区で初のことでした。腎臓移植の黎明期には、免疫抑制剤としてアザチオプリン(商品名:イムラン)とステロイドの2剤しか選択できず、必然的に急性拒絶反応の頻度も高い時代でした。1980年代になってサイクロスポリンA(商品名:サンディミュン)が使用されるようになり、移植腎の長期生着の頻度が高くなりました。この頃が当院で腎移植が最も多かった時代であり、月1例程度を計画的に行っていました。
そして1990年代からはFK-506(商品名:プログラフ)、2000年代からはMMF(商品名:セルセプト)の使用が開始され、更に長期のグラフト(移植腎)の生存が得られるようになってきましたが、脳死移植法案の問題が浮上するとともに、全国的に腎移植数は生体/献腎ともに減少しました。しかし、サイトメガロウイルスやカリニ肺炎といった免疫抑制剤服用下に発生する特殊な感染症に対して、その早期診断や治療法が確立し、これにより命を失う症例は激減しています。
2008年になって当院で施行した生体腎175例、献腎28例と腎移植症例は200例を突破し、ここ数年においては福岡県内での献腎移植症例が増加するとともに生体腎移植のオファーも増加してきています(図1)。

図1 当センターの腎移植患者数 (生体腎:178例、献腎:31例)
1987年から1996年の10年間に当腎センターで腎臓移植を受けた患者100名と同時期に透析療法を導入した患者さん(血液透析166例およびCAPD119例)を対象として、その生命予後と治療継続率について1999年の第99回日本外科学会にて発表を行っています。一施設に統一した研究ですが当該患者さんにおいては腎移植が他の透析療法と比較して平均生存率が長いものの有意差はなく、 治療継続率においては血液透析が長い傾向がありました(表1)。これは欧米と異なり日本の透析療法の優秀性を示すものでもあります。研究期間中での治療変更・脱落の原因については表2に示します。
表1 慢性腎不全治療の生命予後と治療継続率
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生存率(%) | 血液透析 | 97.7 | 91.7 | 87.5 | 72.3 | N.S. |
| 腹膜透析 | 98.8 | 96.2 | 94.7 | 73.6 | N.S. | |
| 腎臓移植 | 93.0 | 91.9 | 90.6 | 83.5 | N.S. | |
| 治療継続率(%) | 血液透析 | 92.0 | 78.6 | 74.4 | 58.2 |
p=0.002 vs CAPD |
| 腹膜透析 | 85.5 | 71.6 | 46.1 | 21.6 | N.S. | |
| 腎臓移植 | 90.9 | 83.4 | 64.4 | 45.8 | N.S. | |
(血液透析、腹膜透析症例は64歳以下の非糖尿病症例)
表2 治療変更・脱落の原因
| 血液透析(24/87) | 腹膜透析(53/83) | 腎臓移植(40/100) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 死亡(13) | HDへ変更(18) | 拒絶反応(30) |
| 2 | 腎移植(8) | 腹膜炎(13) | 感染症(3) |
| 3 | CAPDへ変更(3) | 腎移植(5) | 肝障害(2) |
| 4 | 死亡(5) | 悪性腫瘍(2) | |
| 5 | 機能低下(5) | 循環器(2) | |
| 6 | 患者の希望(3) | グラフト損傷(1) | |
| 7 | カテトラブル(2) | ||
| 8 | 腹部手術(2) |
(血液透析、腹膜透析症例は64歳以下の非糖尿病症例)
それから約10年後の調査では、腎移植の成績は更に改善し生体腎移植においては5年生着率、10年生着率ともに良好な成績を示しており(図2)、おそらくは近い将来に10年生着率が80%を超えるものと思われます。術後の患者さんの生存率については図3に示します。

図2 最近の腎移植の成績:生着率

図3 最近の腎移植の成績:生存率
これからの課題としては
1.血液型不適合移植の導入(2010年1月より開始)
2.腹腔鏡下ドナー腎摘出術の導入(2010年9月より開始)
3.長期生着患者さんにおける生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)
の向上のため、更なるステロイド減量による副作用の減少と心血管系合併症・生活習慣病などの予防対策があげられます。
2.バスキュラーアクセス、経皮的血管延長術(PTA)
バスキュラーアクセス(いわゆる内シャント)は血液透析患者さんの命綱ともいうべきものです。週3回4時間程度の透析を10年、20年と安定して行うためには十分な血流を確保でき、また全身的に負担のないバスキュラーアクセスが理想です。
当センターは1968年より血液透析を開始したという経緯もあり、アクセスの作製やシャントトラブル手術においても長年の経験を持っています。最近ではバスキュラーアクセストラブルへの対応として経皮的血管形成術(PTA)の出番が格段に多くなり(図4)、外科的再建を必要とするのは、より複雑なケースとなっています。また導入時より表在静脈が廃絶して内シャントの作製が困難であったり、心機能の低下によって初期より動脈表在化やパーマネントカテーテル、人工血管によるグラフト内シャントを選択する場合もあります。現在の血液透析の水準であれば、若年で合併症が無ければ25年以上の生命予後も期待される時代になりました。このようなケースでは20年以上に渡ってアクセスが可能となるように作製の手順に配慮することは基本的に変わりありません。

図4 バスキュラーアクセス(VA)手術およびPTA症例
3.経皮的血管形成術(PTA:ふうせん治療)について
透析患者さんにおいて、アクセス管理は非常に重要ですが、血管拡張術が施行できる以前は全例手術でしか改善することができませんでした。
しかし、現在ではアクセスの狭窄は早期に血管拡張術を行うことで、閉塞を予防することが可能となっています。当院はアクセストラブルを数多く治療している施設ですが、手術と経皮的血管拡張術を偏ることなく、患者さんにとってどちらの治療法がより良いかを考え選択しています。
経皮的血管拡張術は、平成12年より開始し徐々にその数を増やしており、現在では年間約120件施行しています。自家静脈内シャントや上肢の人工血管内シャントだけでなく、下肢の人工血管内シャントや中心静脈(体幹内)の血管拡張も放射線科と協力して行っているのが特徴です。
また、通常のバルーン(ふうせん)だけでなく、超高耐圧バルーン、カッティングバルーン、オーバーサイズバルーンなどの使用、造影剤アレルギーのある患者さんへの血管内超音波(IVUS)や二酸化炭素による造影による血管拡張術、血栓溶解術、血栓除去術やステント挿入術など様々な技術を用いて加療を行っています。
通常の血管拡張術でも成功率は95%以上ですが、近年では完全閉塞したアクセスの加療も行っており、特に人工血管の血栓溶解・血栓除去術による再開通は、ほぼ100%となり手術を要しなくなっています。
4.IgA腎症に対する扁桃摘出術+ステロイドパルス療法
IgA腎症はその発症機序において免疫学的バックグラウンドの強い疾患であり、わが国の慢性糸球体腎炎からの末期腎不全の原疾患として最も多いと言われています。IgA腎症に対する扁桃摘出術+ステロイドパルス療法は、IgA腎症の寛解・根治を目指す治療法であり、1988年頃より仙台社会保険病院の堀田修医師らを発信源として全国に広がってきています。(IgA腎症根治治療ネットワーク)
当院腎センターでは堀田医師の招待講演を機に1999年5月より同治療を導入し、現在までに約200人の患者さんに行ってきました(図5)。その結果を2009年の第52回日本腎臓学会で当センターの春山直樹医師らが総括して報告しました。

図5 当院におけるIgA腎症に対する扁摘+パルス療法の推移
全体での寛解達成率では、ステロイドの使用期間が1年間であるにもかかわらず、1年70.4%、3年84.8%、5年88.9%(図6)と年数を減るにつれて改善しているのが特徴です。また寛解に達成した症例は1年間のステロイド中止後も3年81.7%、5年86.7%と高い寛解維持率が得られています(図7)。治療開始時の尿蛋白量で分類し、寛解への導入率を見ると一日尿蛋白量1gを境に寛解率が低下する傾向(図8)があり、IgA腎症の発症早期に治療を開始した方がより効果が高いと考えられます。

図6 扁摘パルス療法全体の寛解達成率 (全体143例 平均寛解期間 1.7年)

図7 扁摘パルス療法寛解導入後の寛解維持率

図8 開始時尿蛋白量別の寛解/非寛解/再発
5.二次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術(PTX)
当院でのPTXの導入は1980年代より外科の千葉武彦医師により開始され、1987年からは腎センターの今村敦郎医師の術後管理の下に継続されていました。1993年に安永親生医師が赴任後、年を経る毎に増加して、現在では毎週金曜日に施行され総手術症例は500例以上に達しています。また最近では内分泌内科佐藤薫医師や開業医さんからの紹介で原発性副甲状腺機能亢進症の症例も増えています(図9)。
透析クリニックからの紹介患者が多かったために、一時は手術待機期間が9ヶ月くらいまで延長した時期もありましたが、2008年1月に塩酸シナカルセト(レグパラ®)という革新的な薬剤が登場後、全国的に手術依頼が減少傾向となり、現在の待機期間は2ヶ月程度となっています。
2009年に二次性副甲状腺機能亢進症に対するPTX研究会(JAPS)が立ち上がり、当院からも安永親生医師が世話人として参加して全国透析施設への調査を行いました(JAPSアンケート調査の結果:PDF)。その結果、福岡県においては当センターがPTX紹介先施設として最も多い病院でありました。当センターで初回PTXを受けた200人の患者さん(1990年7月~2002年10月、平均年齢53.6歳、平均透析歴14.2年)を対象とした予後調査(図10)では術後の5年生存率87%、10年生存率79%と同年代で慢性糸球体腎炎が原疾患である透析導入患者さんと比較しても遜色のない成績でした。このような患者の予後を考慮すると、二次性副甲状腺機能亢進症に対しては長期的に有効な確実性の高い治療法を選択する必要があると考えられます。
現在では二次性副甲状腺機能亢進症に代表される腎性骨異栄養症は、骨だけではなく動脈の石灰化を起こして動脈硬化を促進する全身性の病態として、慢性腎臓病にともなう骨ミネラル異常(CKD-MBD;Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder)と呼称されるようになってきています。

図9 当院での副甲状腺摘出術症例数の推移

図10 初回PTX術後生存曲線(Kaplan-Meier analysis)
腎センターの活動
1.まめまめ教室

当院では2007年7月より保存期慢性腎不全の患者さんとそのご家族を対象に腎臓病教室(“まめまめ教室”)を開催しております。日頃の外来診察時には時間も足りず分かりにくかったことを補足し、様々な疑問にお答えする場としています。
第一部(奇数月)では、医師より腎臓の構造・働き・腎不全の症状についてご説明し、その進行をどのようにして遅らせ透析治療を先にのばすかについて、ポイントを患者さんと一緒に勉強しています。薬剤師より降圧薬・利尿薬・吸着薬等、腎不全の際処方される薬剤の効果・特徴や注意点についてご説明します。
第二部(偶数月)は看護師より自己管理(体重測定・血圧測定など)、運動療法の大切さについてご説明します。栄養士より保存期における食事療法(たんぱく質の制限、十分なエネルギー確保、塩分制限、カリウム制限など)と、楽しく長続きするポイントをお話します(図11)。
慢性腎臓病に対する理解をより深め、日頃負担となるような治療や制限の意義を再認識して頂くことで、より効果的にストレスが少なく治療を長く続けられることを目的としています。
教室は月一回(原則第一木曜日)開催しています。ご希望の方で、当院にカルテのある患者さんは腎センター外来までお気軽にお問い合わせください。
2.慢性腎臓病(CKD)の啓蒙活動
現在は慢性的な腎臓病を総称して「慢性腎臓病」と呼ぶようになっています。もっと正確に言うと、腎機能障害(腎臓の機能が60%程度に低下)や検尿異常、腎臓の形態異常などが3ヶ月以上持続するときに慢性腎臓病と診断することになっています。
この「慢性腎臓病」という言葉ができた背景には、腎臓の病気は診断名が難しく、患者さんや行政、保健機関などにも理解していただくことが難しいかったため、簡単に診断し、早期に治療を進めるためには誰でも理解できる診断にした方が良いということでこの言葉ができました。早期に治療することで、IgA腎症の治療の項にもありますが、ほとんどの方が完治を望める腎臓病もあるのです。
診断の例をあげると、健康診断で2年連続検尿に異常がある方や、エコーで腎臓内にふくろ(嚢胞)ができている方は、慢性腎臓病である可能性が高いということになり、診断の基準を知ってさえいれば、医師でなくても誰でも診断できます。
この慢性腎臓病は、実は非常に多く、日本では約8~9人に一人も罹患しており、すでに国民病であると言われています。特に高齢者では多いのですが、北九州では60歳代では5人に1人、70歳代では4人に1人は慢性腎臓病の可能性があるようです。
また、慢性腎臓病の怖さは、腎機能が廃絶して透析を受けなければいけなくなると言うことだけではありません。脳卒中や狭心症・心筋梗塞などの心血管合併症を起こす頻度が約3倍に上昇することが本当の怖さなのです。慢性腎臓病や心血管合併症は高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と深く結びついているため、生活習慣の改善が重要と言われています。
当院腎センターの柳田太平医師は、数年前より、この慢性腎臓病の啓蒙活動を地道に行っています。区役所、公民館、図書館などいろいろな場所で慢性腎臓病予防・早期発見のための市民講座や、すでに慢性腎臓病になっている方への腎臓病講座など、市民向けの講演を多数行っています。また、地域の健康推進委員、保健師、栄養士向けの腎臓病講演も行ない、より多くの方に慢性腎臓病を知っていただくよう活動しています。(ご相談があり、都合が合えば、講演に伺います)
また、医師会や行政、そして腎臓専門医からなる慢性腎臓病検討会でも活動し、特定健診にて腎臓の異常を指摘された方を、どのように、早期診断・治療していくかを検討しています。
3.CAPD交流キャンプ

当院では1980年1月より新しい透析方法としてCAPD(連続携行式腹膜透析)を導入しています。1990年2月には第1回CAPDサマーキャンプと称して、CAPD患者さんとの研修旅行(阿蘇)を実施しました。在宅医療であるCAPDは、週3回通院を必要とする血液透析と比較して自由度の高い透析方法です。そのメリットを生かして、旅行を通して患者さんや患者家族どうしの交流と情報交換を行い、スタッフによる教育講義なども組み合わせたものです。現在ではCAPD交流キャンプと称して、CAPD患者さんのみならず、元CAPDの血液透析患者や移植患者さんも合流して、その経験を話す旅行ともなっています。H20年は鹿児島の篤姫ツアー、H21年は長崎伊王島、H22年は大分の別府の温泉旅行でした。
社会福祉法人  済生会支部
済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院
- TEL093-662-5211
- FAX093-671-3823
- 〒805-0050 福岡県北九州市
八幡東区春の町五丁目9番27号 - 交通アクセス